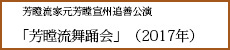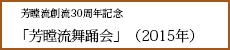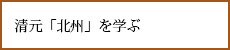ホーム > 芸・知・学 |
芸・知・学
清元「北州」を学ぶ
この「北州」は清元の名曲として知られ、江戸千代田城から北の新吉原に、その題材を求め今から194年前の文政元年(1818年)に作詞大田蜀山人、作曲川口お直によって、お座敷浄瑠璃として世に発表された作品。
作詞の大田蜀山人という人は非常に粋な人であったらしく、よく吉原に遊び、この「北州」も吉原の遊女の部屋で書いたという説がある。作曲の川口お直という人は、元吉原の芸者さんで、後の料亭「川口」を出し大いに繁昌したと言うことである。お直さんは清元はもとより、河東節も巧みに語り、三絃にも秀でていたと言われている。
では何故この曲が名曲と言われているのか?その姿をさぐって行こうと思う。
先ず“凡千年の鶴は…”の唄い出しは能がかりの置浄瑠璃で格調高く始まり、初春の祝儀をのべている。
その後“霞の衣えもん坂…”からは、がらりとくだけた調子となり、吉原の廓の中に入って行く、そこには新年を祝う松飾りが背中合わせに並び、松飾りのかざり海老の上には、それぞれの茶屋の家名を記した大黒傘が立ててある。やがて正月が過ぎ、仲の町には桜が立ち並び春の訪れを感じる。
“柳桜の仲の町…”のところの曲がまた素晴らしく、桜時分になると吉原は桜見物をかねて粋客が多く集まり、茶屋も妓楼も賑やかとなり、遊女たちの仕事が忙しくなる、というのはそれだけ遊女達に苦しみがかかることで、作曲の川口お直はこの部分にわざと遊女たちが張見世に出る時に使われる「清掻」という華やかな旋律を哀愁をおびたスローテンポのリズムにしたところは、まさに吉原を知る者だけが、考えられるものであり「北州」という曲の最高の一節とも思われる。
この曲の中には色々な人物が登場するが、何といっても吉原の主役である遊女たちが大田蜀山人によってよく描かれている。
その悲劇性を考えると、吉原の四季折々の内、七夕を迎えると、遊女たちは織姫と牽牛のことを思い浮かべ、一年に一度しか逢えない境遇を哀れみ、わが身はそのようになりたくない、好きな男といつも逢っていたいと語り合い、情人の紋どころを切り抜き笹に付けて供える。こうした情景を“星の痴話ごとさざめごと…”という歌詞で表現している。
“露打掛けの菊かさね…”と露と菊を持って来ることによって秋を匂わせ、“禿引込み突出しの…”という遊女になるまでの三段階の時を唄っている。ここで志川節子氏の著作「手のひら、ひらひら」の中に出て来るように、吉原に「上ゲ屋」とか「保チ屋」という仕事をする人間が存在し、引っ込みの間にこの仕事士によって、遊女教育を受けたのだとすると恐ろしさを感じる。
そして秋も過ぎ冬になると、蜀山人は“約束かたき神無月、誰が誠より本立の…”と唄い、ここは中納言藤原定家のうたを引用したと言われているが、何故このうたをここに持って来たかが問題で、前に痴話言というと奥さんになりたいと書いたが、ここでは更にその願望を強め、神無月は神様が出雲に出向き居ないのならば、この時だけでも好きはお方の妻となっても罰は当たらないという、遊女の悲しい思いを言いたかったのであろう。
“山鳥の尾の酉の市、姉許ゆけば千鳥足…”とうたい、ここでは当時相思相愛の男と女が別居していることを山鳥の夫婦といい、尾の長い山鳥の尾をとって短くするように、一日も早く一緒に暮らしたいと願い、たとえ酒に酔って千鳥足でもよいから、私の許に来てほしいと願っている。
この後は吉原から離れ四季折々の風景をのべ、最後は清元の栄えんこと、そして日本の国が安らかな国であることを願い、この曲を結んでいる。
名曲である「北州」を舞台にかけ、表現していくにあたり、踊り手は作詞の大田蜀山人と作曲の川口お直の吉原に対する心情を捕えることが大切で、そのためにも内容をよく理解して、自分なりに演出し、表現することが大切だと思います。
(文責 初代芳瞠宣州)
【芸知学】では日本舞踊をより興味深く、楽しく面白く接して頂くために、先代芳瞠師より伝え聞いているお話や、先人たちの資料に基づき、いろいろ綴って参ります。
この「北州」は清元の名曲として知られ、江戸千代田城から北の新吉原に、その題材を求め今から194年前の文政元年(1818年)に作詞大田蜀山人、作曲川口お直によって、お座敷浄瑠璃として世に発表された作品。
作詞の大田蜀山人という人は非常に粋な人であったらしく、よく吉原に遊び、この「北州」も吉原の遊女の部屋で書いたという説がある。作曲の川口お直という人は、元吉原の芸者さんで、後の料亭「川口」を出し大いに繁昌したと言うことである。お直さんは清元はもとより、河東節も巧みに語り、三絃にも秀でていたと言われている。
では何故この曲が名曲と言われているのか?その姿をさぐって行こうと思う。
先ず“凡千年の鶴は…”の唄い出しは能がかりの置浄瑠璃で格調高く始まり、初春の祝儀をのべている。
その後“霞の衣えもん坂…”からは、がらりとくだけた調子となり、吉原の廓の中に入って行く、そこには新年を祝う松飾りが背中合わせに並び、松飾りのかざり海老の上には、それぞれの茶屋の家名を記した大黒傘が立ててある。やがて正月が過ぎ、仲の町には桜が立ち並び春の訪れを感じる。
“柳桜の仲の町…”のところの曲がまた素晴らしく、桜時分になると吉原は桜見物をかねて粋客が多く集まり、茶屋も妓楼も賑やかとなり、遊女たちの仕事が忙しくなる、というのはそれだけ遊女達に苦しみがかかることで、作曲の川口お直はこの部分にわざと遊女たちが張見世に出る時に使われる「清掻」という華やかな旋律を哀愁をおびたスローテンポのリズムにしたところは、まさに吉原を知る者だけが、考えられるものであり「北州」という曲の最高の一節とも思われる。
この曲の中には色々な人物が登場するが、何といっても吉原の主役である遊女たちが大田蜀山人によってよく描かれている。
その悲劇性を考えると、吉原の四季折々の内、七夕を迎えると、遊女たちは織姫と牽牛のことを思い浮かべ、一年に一度しか逢えない境遇を哀れみ、わが身はそのようになりたくない、好きな男といつも逢っていたいと語り合い、情人の紋どころを切り抜き笹に付けて供える。こうした情景を“星の痴話ごとさざめごと…”という歌詞で表現している。
“露打掛けの菊かさね…”と露と菊を持って来ることによって秋を匂わせ、“禿引込み突出しの…”という遊女になるまでの三段階の時を唄っている。ここで志川節子氏の著作「手のひら、ひらひら」の中に出て来るように、吉原に「上ゲ屋」とか「保チ屋」という仕事をする人間が存在し、引っ込みの間にこの仕事士によって、遊女教育を受けたのだとすると恐ろしさを感じる。
そして秋も過ぎ冬になると、蜀山人は“約束かたき神無月、誰が誠より本立の…”と唄い、ここは中納言藤原定家のうたを引用したと言われているが、何故このうたをここに持って来たかが問題で、前に痴話言というと奥さんになりたいと書いたが、ここでは更にその願望を強め、神無月は神様が出雲に出向き居ないのならば、この時だけでも好きはお方の妻となっても罰は当たらないという、遊女の悲しい思いを言いたかったのであろう。
“山鳥の尾の酉の市、姉許ゆけば千鳥足…”とうたい、ここでは当時相思相愛の男と女が別居していることを山鳥の夫婦といい、尾の長い山鳥の尾をとって短くするように、一日も早く一緒に暮らしたいと願い、たとえ酒に酔って千鳥足でもよいから、私の許に来てほしいと願っている。
この後は吉原から離れ四季折々の風景をのべ、最後は清元の栄えんこと、そして日本の国が安らかな国であることを願い、この曲を結んでいる。
名曲である「北州」を舞台にかけ、表現していくにあたり、踊り手は作詞の大田蜀山人と作曲の川口お直の吉原に対する心情を捕えることが大切で、そのためにも内容をよく理解して、自分なりに演出し、表現することが大切だと思います。
(文責 初代芳瞠宣州)
【芸知学】では日本舞踊をより興味深く、楽しく面白く接して頂くために、先代芳瞠師より伝え聞いているお話や、先人たちの資料に基づき、いろいろ綴って参ります。